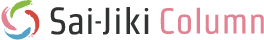二十四節気
大寒だいかん:新暦1月20日頃
冷ゆることの至りて
甚だしきときなればなり(暦便覧)
「大いに寒い」という通り一年でもっとも寒さの際立つ時期とされ、体を小さくしてじっとやり過ごす日々を迎えます。大寒の頃には一月二十日の二十日正月を迎え、盛大に祝った正月ともしばしのお別れ。心も体も通常運転に切り替えることになります。また厳寒ではありますが同時に冬の終わりでもあり、次はいよいよ待ちに待った春の到来ということに。四季のあいだにはそれぞれ「節分」がはさまって切り替えの調整をしてくれますが、冬春間の節分は特に一年の切り替えでもあり行事も盛りだくさん。春の準備に忙しくて寒さをすっかり忘れていた、などとなれればよいのですが。
七十二候
款冬華ふきのとうはなさく:1月20日頃
 ふきのとうが顔を出しはじめる時期。実際にはふきのとうの芽吹きは春先、雪解けに前後した時期なので暦とは少々のズレがあります。ふきは雌雄異株で、ふきのとうがほころんだとき白い花のみえるのが雌株、やや黄色味がかっているのが雄株と見分けます。この頃には二十日正月があり、主に関西地方では正月行事の締めくくりとして年取り魚などを入れた最後のお雑煮が食べられます。
ふきのとうが顔を出しはじめる時期。実際にはふきのとうの芽吹きは春先、雪解けに前後した時期なので暦とは少々のズレがあります。ふきは雌雄異株で、ふきのとうがほころんだとき白い花のみえるのが雌株、やや黄色味がかっているのが雄株と見分けます。この頃には二十日正月があり、主に関西地方では正月行事の締めくくりとして年取り魚などを入れた最後のお雑煮が食べられます。
水沢腹堅みずさわあつくかたし:1月25日頃
沢の水に氷が張り詰める時期。流れる水は凍りづらいといわれますが、それさえも容赦なく氷結させてしまうこの時期の寒さがよくわかる表現です。水面に張った薄い氷はセミの羽根にたとえて「蝉氷」、波模様に固まった氷は「氷の花」。言葉が可憐で美しいほど、冷たさが際立って感じられるのはなぜでしょう。雪の女王、雪女、氷の微笑。氷は美女とも不思議と相性がよいようです。
鶏始乳にわとりはじめてとやにつく:1月30日頃
「ニワトリはじめて鳥屋につく」と読み下し、ニワトリたちが産卵のため小屋にこもる時期ということ。ニワトリは東南アジア原産の野生種が家禽化されたもので、人間とは相当に長いおつきあいですがそれでも寒い冬はまだ苦手なのかもしれません。
立春をスタートとする七十二候はこれをもって一巡、締めくくりを迎えます。鳥屋にこもったニワトリは卵をあたため、やがてかわいらしい雛の誕生へ。立春にむけ、新しい一年へのバトンタッチを象徴するような候になっています。
季節のことば
三寒四温さんかんしおん
もとは満州地方や朝鮮半島辺りにいわれていた冬のことわざで、三日寒い日が続くと四日暖かい日がやってくるという気候風土をあらわしたもの。正式な気象用語ではありませんが、シベリア気団の影響によってこの地域ではある程度規則正しく七日周期の気温変化があるものとされました。日本にも言葉としては輸入されたものの、太平洋側の気圧の影響なども受ける日本列島の冬にはあてはまらないものでした。
結局日本では本来の意味をはなれ、春先、暖かくなったと思いきやまた寒い日に逆戻り…という頃の気候を表すのに用いられるようになりました。ことわざのリサイクルといったところで、「サンカンシオン」とリズムよく耳に響く言葉を惜しんだ先人がいたのでしょうか。
二十日正月はつかしょうがつ
元日の大正月から十五日の小正月と打ち続いてきた正月行事もいよいよ終了。最後の〆となるのが二十日正月で、年取り魚の鰤も食べ納めとなり骨まで雑煮に入れることから「骨正月」ともいいました。もっとも関西ではわりと盛んだった二十日正月の行事も東京辺りでは早くに廃れ、東日本では小正月明けをもって正月の終わりとする感覚が主流だったようです。
小正月に供えた団子などを下げることから「団子正月」の名もあり、餅花や繭玉など小正月の供え物は総じてこの日に下げられるものでした。
春隣はるとなり
春近し、春間近、春遠からじ…詩歌の世界には春を待ちわびる心を表すことばがあふれています。雪国ともなれば、現代であってもやれ除雪だタイヤの交換だと外出の準備に一苦労。今ほど便利でなかった時代にはいかばかりだったことでしょう。一日も早く春が来て欲しい、そんな気持ちは冬が厳しければ厳しいほど強まるもので、「春隣」には春はすぐそこ、という慶びと切望が織り込まれています。
直接「春」ということばを使わずに思慕を表した美しい言い回しが「日脚伸ぶ」。冬至からひと月を経て、日一日と昼が長くなるさまをあらわしたものです。
冬の終わりを惜しむように春先に降る雪、というと「なごり雪」が思い浮かびますが、実はこのことばは1970年代のヒット曲「なごり雪」が初出で、作詞家による全くの創作単語でした。今ではすっかり一般名詞として定着し、俳句に読まれても違和感を覚えない方も多いことでしょう。
この時期の風習や催し
初地蔵
初湯、初日、初芝居と初ものづくしの正月ですが、神社やお寺の一年最初のお祭り、縁日も「初◯◯」とご祭神やご本尊の名前をつけてよびました。「初水天宮」は正月五日、「初薬師」は同八日、正月最初の寅の日は「初寅」で、これは毘沙門天のご縁日。落語で有名な「初天神」は天神さま=天満宮のご縁日で二十五日となっていました。
お地蔵さま、地蔵菩薩のご縁日は四のつく日と決まっていて、特に正月二十四日が「初地蔵」とされました。とげぬき地蔵で名高い巣鴨の高岩寺の初地蔵は今もたいへんに賑わいます。とげぬき地蔵は「すぽっとトゲをぬくように苦しまず往生できる」ということからお年寄りの信仰を集めるようになりました。巣鴨商店街の一帯は「おばあちゃんの原宿」として、モンペや赤パンツなどなかなかよそでは見られないイキな品揃えでご年配のハートをがっちりキャッチしています。
凧あげ
女の子の羽根つきに対して、男の子の正月の遊びといったら凧あげです。冬の田畑は凧あげの格好の遊び場になっていましたが、昨今の住環境では広い場所を必要とする凧あげは難しくなっているのかもしれません。昔は東京でも「正月の空が黒くなる」といわれるほど多くの凧があがっていたそうです。
凧あげは季語としては春のものとされます。これは「立春に空を見上げるとよい」という言い伝えから立春のころに凧あげをする風習があったからともいわれ、また端午の節句に子供の健康を願って凧あげが行われたことも影響しているよう。今でも凧あげ大会といえば一月と五月がメインシーズンで、春の連休にあわせて開催される静岡県浜松市のはままつ祭りでは、何百という凧が一斉に空を舞う凧揚げ合戦が行われます。浜松には100年以上続く凧職人の家系もあるというから、地域での愛されようがわかるというもの。
東京北区の王子稲荷では二月の初午、二の午の日に凧市が立って多くの人を集めます。凧は風を切ることから火除けのまじないという意味もあり、江戸で凧が愛されたのはそうした理由も大きかったようです。

浜松祭り凧揚げ
恵方巻
節分の晩に、その年の恵方(縁起のよい方角)を向いて太巻きを丸かじり。一本完食するまで口を離すのもおしゃべりも禁止というストイックなルールにもかかわらず、今やすっかり節分の風物詩となりました。恵方巻は古い年中行事事典などにはその項目すら見当たらず、相当に新しいイベントだということがわかります。
スーパーのチラシなどには恵方巻の由来がいろいろ書かれていますが、俗説や悪く言えば創作の域を出ないものもあるようで、研究者によれば節分のスーパーなどで「幸運巻き寿司」の名前がぼちぼち聞かれ始めたのは1980年代の関西方面とのこと。
そのきっかけは、大阪の海苔業界が海苔の販路拡大のために始めた巻き寿司の一大プロモーションで、70年代に道頓堀で開催された「節分巻き寿司早食い大会」を契機に一気に知名度をあげたらしいことがわかっています。こうしてわずか10年ばかりで関西の「伝統文化」となった節分巻き寿司が大手コンビニチェーンによって全国に紹介されたのは平成に入ってからで、「恵方巻」の名前もこのコンビニによって採用されたもの。爆発的人気となったのはつい最近、21世紀になってからのことです。
ずいぶん浅い歴史だなというがっかり半面、「新しい年中行事」が産声をあげる貴重な瞬間に立ち会っているのだと思えば感慨深いような気もしてきます。最近ではさらに斬新な「恵方ロールケーキ」といったニューフェイスも登場しています。
季節の食・野菜・魚
蕗の薹ふきのとう
「雪もまだ残る田の畔に顔を出したふきのとうを見つけると、ようやく春の訪れを実感して気持ちもはずんできます。「薹」というのは花茎のことで、ここがすくすく伸びて立ち上がると、大きいものでは30センチ近くに成長することもままあります。ここから出た言葉が「薹が立つ」で、旬を過ぎ食べ頃を逃したということから人間に使うときもあまり良い意味とはされませんね。
ふきなど春の山菜が持つ独特の苦味には、食べることで冬仕様だった体のスイッチを春対応に切り替える効果があるそうです。適度な苦味は食も進むもの。進んで食べたい旬の食材です。てんぷらなどでも美味しいふきのとう、一番のオススメは細かく刻んだふきのとうを味噌と適量の砂糖で和えた「ふき味噌」です。ほろ苦さが味噌の風味と最高に絡み合い、鼻から抜ける春の香りにごはんがいくらあっても足りないほど箸が進んでしまいます。
ただ、ふきのとうとりに夢中になって他人の田んぼやあぜにまで入り込むと、地元の人からは白い目でみられてしまいます。節度を守って春の風物詩を楽しみましょう。

金柑きんかん
原産地は中国の南方で、主な分布地も中国と日本となっています。柑橘類には珍しく皮ごと食べられる果実は、光沢のある鮮やかな色味から縁起物としておせち料理にも用いられます。「きんかん」と「ん」が二つも付くことから「運がつく」としてよろこばれたこともあるようです。常緑の低木で、木全体に鈴なりに実をつけた様子がまたおめでたいということで庭木にも使われていました。
おせち料理などでは甘露煮にしたものが一般的ですが、最近ではより生食に適した実に改良された甘くやわらかい品種も登場し、ぶどうやメロン並みの糖度を叩き出すものまで登場しているとか。南方のものだけあって日本でも出荷量は宮崎県が堂々の第1位、あとにも鹿児島、熊本と南国が続きます。

海鼠なまこ
寒い冬、身も締まり旬を迎えたナマコ。11月の漁解禁を待って各地で水揚げがはじまります。
「あんなモノに旬なんてあるの?」などと思っては大変失礼。身は酢のものや乾物に、内臓は塩辛にと余すところなく頂けるナマコは、コラーゲンやコンドロイチンなども豊富で滋養強壮にも効果ありという素晴らしい食材です。
コリコリした食感を楽しむ酢の物も美味ですが、ナマコの利用法の第一は乾物。中華料理の食材として重宝され、干ナマコは江戸時代には重要な大陸への輸出品となっていました。
腸の塩辛コノワタはウニ、カラスミとともに三大珍味の一角を占め、卵巣の干物であるクチコに至ってはグラムあたりの値段が最も高い食材のひとつとされ、一枚五千円、六千円もざらなもの。クチコ一枚作るのに必要なナマコは数十キロともいわれる手間ヒマのかかった高級品なのです。卵巣を干すクチコづくりの様子も冬の風物詩にあげられます。
河豚ふぐ
「死の危険を冒してまで、毒のある魚を食べるなんて…」と、外国の方からは奇異に見えることもあるという日本のフグ文化。日本でも豊臣秀吉はフグ食禁止令を発し、徳川幕府も中毒死はたいへん不忠、不名誉な死にあたるとしてたびたび禁令を出したようですが、今日のフグ食文化の豊かさを見れば「それでも食べたい」とこっそり調理術を進化させてきた先人の食欲に脱帽、感謝。
「あたると死ぬ」とシャレをきかせた江戸っ子のフグの呼び名は「てっぽう」。フグのちり鍋をてっちりといって討ち死に覚悟でほおばりました。フグ毒の正体はテトロドトキシンという成分で、一匹で人間の大人数十人分の致死量になるといわれる猛毒です。フグは餌となるヒトデなどから摂取し内臓に溜め込んでゆきます。フグを食べると微量の毒でしびれるため、体がその快感を覚えてまた食べたくなってしまうんだなどという話もありますが、真相やいかに。猛毒の卵巣をぬか漬けにすることで無毒化した北陸の伝統料理もあります。
江戸時代には鍋の具にすることが多かったフグを初めて刺身にしたのは、幕末の下関といわれます。一説には高杉晋作ら長州の志士がはじめたのだとも。命知らずな男達にはふさわしいエピソードのようです。

てっちり鍋
- 新版 美麗写真でつづる 日本の七十二候 晋遊舎
- 二十四節気と七十二候の季節手帖 山下 景子著 成美堂出版